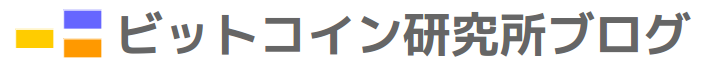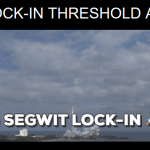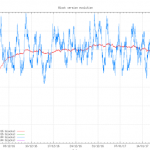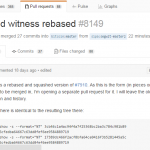レポート「アルトコイン図鑑」では30種類以上のコインの概要と見通しを解説(詳しく)
本日の朝、遂にSegwitがアクティベートされた。
Segwitのアイデアが発表されて、実装が始まり、長いデプロイプロセスを経て、約2年越しの実現である。感慨深い。
Segwit導入は、ブロックサイズが実質的に拡張され、トランザクション展性の問題が解決するほか、Sighashの問題の解決、スクリプトVersionの導入など、広範にわたる改善となる。特定の新機能というより、OSレベルでのメジャーアップグレードと捉えると理解しやすいだろう。
さて、早速Segwitのトランザクションが発行されているようだ。Bitbank社が先ほどツイートしたところによると、世界初のネイティブSegwitトランザクションを発行し、マイニングされたようである。
それを下記に示す。
https://www.smartbit.com.au/tx/f91d0a8a78462bc59398f2c5d7a84fcff491c26ba54c4833478b202796c8aafd
少し技術的なところを見ていこう。

まず、InputとOutputのところを見ると、通常はビットコインアドレスが表示される部分が、Unable to decodeと赤字になっている。つまり、Segwitトランザクションのため(まだ)表示出来ないという形である。
トランザクションの中身に踏み込もう。
まずは、Inputのところであるが、署名(ScriptSig)部分が完全になくなり、Witness Data領域に移動したことがわかる。
<Segwit txのInput>

比較のために、典型的な従来のトランザクションのInputを見てみよう。

非常にデータ量が多いことが分かる。この署名データ部分が、まるまる無くなるのだから、圧縮効果は大きい。
次に、Outputを見てみよう。Segwitのトランザクションでは、ゼロで始まるSegwitのバージョンNoのあとに、Publickeyのハッシュを並べたものがOutputになる。たいへんシンプルだ。

典型的な従来のトランザクションも比較のために引用する

効果は目で見てわかるだろう。
実際に、このSegwitトランザクションだが、1つのインプットを2つのアウトプットに送り、さらにOP_RETURNによるメッセージまで入れて、159 bytesとなっている。通常この手のトランザクションを作ると300-400 bytes近くなるので、半分程度になるということだ。その分手数料も安く済む。
さて、一般のユーザーがSegwitのトランザクションを送れるようになるためには、使っているウォレットが対応する必要が有る。現在対応済の一般向けウォレットは存在していないが、Trezorがいち早くリリースを宣言しているので、ここ2−3週間のうちに対応するものと期待したい。
・おしらせ
ビットコイン研究所の有料版サロンでは、平易な言葉で最近の技術や業界事情などについて解説するレポートを毎週配信しています。
暗号通貨について、もっと知りたい、勉強をしたいというかたに情報を提供しています。サロン内では疑問点も質問できます。
一度登録いただけると100本以上の過去レポートが読み放題で、大変お得です。レポート一覧がこちらのページありますので、よろしければいちど目をとおしてみてください。