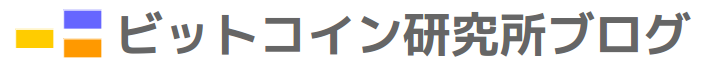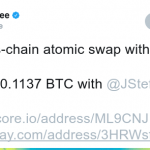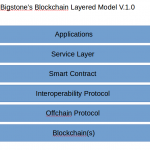レポート「アルトコイン図鑑」では30種類以上のコインの概要と見通しを解説(詳しく)
ビットコインやライトコイン、ビットコインキャッシュ、リップルのXRPなど、もっぱらお金としての機能のみを持つトークンをマネタリートークンという。
前回の、ユーティリティトークンの価値算定においては、ファイルストレージや計算といった実用機能を提供するトークンの価値を算定した。これらのトークンの価値はユーザーが実感する実用価値に等しいとした。
一方で、ビットコインに代表されるマネタリートークンには、そうした実用的な価値は全く存在しない。純粋にお金としての機能しか持たない。
このため、ユーティリティトークンや、配当型のトークンとへ別の価値算定の理論が必要となる。
理論については、主に2つの説があるが、議論が割れている。
交換価値説と採掘価値説である。
交換価値説
交換価値説は、現代的なお金の理論だ。お金自体、それ自体には価値は存在せず、もっぱら支払い手段として便利であるということによってその価値が生まれるとするものである。たとえば、ドルや日本円などの紙幣は、もはやゴールドの裏付けも存在せず、中央銀行は好きなだけの紙幣を刷っている。それでも紙幣は現実にものやサービスの支払いを媒介しており、お金として通用している。
それは、支払い手段として便利であり、低コストであり、利便性があるからだ。たとえば日本円であれば、日本国内においては誰もがそれを受け取るので、日本円を持っていればいついかなるときでも、任意のサービスと交換することができる。そのようなものは、他人もうけとるので、誰もがほしいものとなる。つまりそこにお金としての共同幻想がうまれる。受け取る人がいるかぎり、コインには価値がある。
経済学者の岩井克人氏は、貨幣の価値について「貨幣はみんなが価値があると思い込むから価値がある」としている。鶏と卵であるが、政府紙幣では政府が紙幣のが流通を保証することでこの共同幻想を作り出すことに成功している。日本国内では紙幣の受け取りは保証され、拒否することはできず、また徴税は日本円によっておこなわれる。このことが、日本円紙幣の強い交換性を生み出し、共同幻想を強化する。信用のみで価値を生み出しているので、これらを「信用貨幣」という。
暗号通貨においては、このような政府による流通の保証というものがないので、どのようにして共同幻想をつくるかという点が課題となる。基本的には、そのコインでものが買える店舗などが増え、使える場面が増え、交換性が増せば増すほど、ネットワーク効果がはたらき、さらに交換性が増していく。
暗号通貨により支払いができる場面や、実際の支払いの量と速度が決定的に大事であり、そのため、この交換価値説を支持する人は、コインが使われる場面の拡大とともに、手数料が十分安く、支払いが早いことを重視する。それらは価値の大きな構成要因だからだ。
交換価値説では、コインの価値の源泉はもっぱら交換可能性にあるため、根本的には紙幣と同と考えることができる。中央の発行体があるかないか、上限がきまっているかといった仕組みの上での違いはあるものの、価値が生まれる仮定は紙幣と同様である。つまり、交換価値説のコインは、紙幣を仮想通貨化したものであると言える。
「誰かが受け取るから価値がある」
交換価値説では、交換行為が価値を生むので、媒体となるお金は何でも構わない。紙幣がタダの紙であるのにお金として機能するわけなので、紙であってもよい。
竹中平蔵氏の「経済ってそういうことだったのか会議」という本で、牛乳瓶の蓋がお金として流通する話がでている。小学校のクラスで、牛乳瓶の蓋をあつめることが流行りだし、その蓋があたかもお金のように扱われたというものである。
このように牛乳瓶の蓋であっても、そこに信用が生まれて交換価値が生じれば、お金としての機能を果たすという好例である。
さて、このようなコインの場合、コインの価格はどのように決まってくるだろうか?
交換価値をベースとしたコインは、基本的にはそのコインがつかわれる経済圏の活動の総量を、流通速度で割ったものに等しい。
つまり、ある経済圏の経済活動の規模=GDPを交換するための、必要十分なコインが流通するという等式である。これはマクロ経済におけるマネーサプライの理論と同様である。ただし、暗号通貨には銀行による貸出のような信用創造機能はないので、もっとシンプルになる。
つまり、あるコインの時価総額は、
コイン時価総額
=マネーサプライ(M)
=コイン経済圏の活動総量(GDP)/ コインの流通速度(V)
となる。
M=GDP/V
というシンプルな式である。
交換価値説においては、コイン自体はどのように生み出されたものであってもよいし、実態がなんであるかは問わない。牛乳瓶の蓋であってもお金として機能するので、なんであれ交換媒体に適したものであれば良い。
交換が価値を生むので、紙幣と同様に無から生み出されたトークンであっても構わない。20円の原価で生まれた(一万円札の例)が、1万円として流通していてもおかしくはないのである。また、コインの初期配布や利子も問題にならない。取得価格がゼロ(プレマイン)であったり、POSにより(ただコインを持っているだけで)追加のコインを手に入れることが出来たとしても、それらは交換価値には影響しない。P2Pでなくても中央の管理者がいてもよく、またブロックチェーンですらなくてもよい。オラクルDB上の数字でもよい。
この立場からすると、マイニングは単なる電気のムダであり、マイニングなしにブロックチェーンが十分セキュアに維持できれば、そのほうが優れているとする。
多くは、交換価値説を支持しているように思える。暗号通貨ユーザーの大半は、交換価値説こそがコインの価値を生む唯一の源泉であると考えているようだ。
また、交換価値説では、価値の保存の機能は後から生じるとしている。交換価値がまず有りきで、それが十分に達成されると、通貨として機能し始めるので、当然ながらそれを貯蔵することもできるようになり、価値の保存としても使えるようになる。
一方で、交換価値説の前提である、経済活動を支える通貨として暗号通貨が機能するかどうかについては、一定の疑念を挟まねばならない。通貨として価値の交換を支えるには、当然ながら、価格の安定が必要であるという指摘である。一年に価格が何倍にも変動する通貨は、交換媒体としては不適切である。
価格を安定させるためには、経済規模にあわせて供給量を自動的に調整する必要がでてくる。適切なサプライ量でなければ、インフレかデフレをおこしてしまうからだ。現在の多くの仮想通貨は供給量や供給スケジュールを固定としており、この点からみれば、通貨としては機能しない可能性がある。
紙幣の場合はマネーサプライのコントロールを中央銀行が担っているが、暗号通貨の場合は分散的なアルゴリズムによって自動的に供給量を調整することができる発明がなされるかもしれない。
ただし、供給量の調整がなされた場合「暗号通貨は発行上限があるから価値がある」という話は崩れる。交換価値説では、発行上限による希少性ではなく、あくまで交換価値により価値が生まれるため、発行上限の撤廃は問題がないと思われる。
採掘価値説

もう一方の主張は、採掘価値説と呼ばれる。
これは、トークンの価値が、それを得るのに費やされるコストと一致するという理論である。これはゴールドがなぜ価値を持つかという議論に等しい。
ゴールドは何らの実用的な価値をもたない。確かに装飾品や工業用として使われる場面はあるが、ゴールドの大半は装飾品になるよりも、各国の中央銀行の金庫に置かれたままである。
ゴールドは、価値の交換媒体としては不便である。重く、携帯性がなく、即時に分割ができない。
ゴールドで買い物をしようとするひとも存在しない。財布にゴールドをいれておき、それでコーヒーを買う人も存在しないだろう。つまりゴールドは、頻繁な交換や流通、安い決済・支払い手段といった交換価値説の観点からみると、価値が生み出されるような特性を持ち合わせていない。
しかしながら、ゴールドには価値があると考えている人が多いのはなぜだろうか?交換価値に乏しいのに、なぜ価値がうまれるのだろうか?
それは、ゴールドは金属的・化学的性質の条件が揃っていることにより、「富の量を示す証明」という特殊な用途として使うことができるので、価値があると考えられている。
ゴールドは、無から作り出すことができない。ゴールドを手に入れるには、地下からコストをかけて掘り出すしかない(もしくは市場で時価で購入するかの2択である)。ゴールドは、錬金術が成功しなかったように、地球上では他の金属から作り出すことができず、恒星のコアのなかで、核融合によってのみ生成される。現在地球上にあるゴールドは、遥か昔の超新星爆発により撒き散らされた星の残骸の中にあったもので、地球上に埋蔵されているゴールドの量は上限がある。
採掘された1kgのゴールドが目の前にある意味を考えよう。ゴールドの真偽は、比重によって容易に検証でき、もし本物のゴールドが目の前に存在しているなば、それは無から作り出すことはできないので、誰かが膨大なコストを払って掘り出したものであることは、世の中の人の誰もが疑いを挟むことができないかたちで、明示される。
つまり、ゴールドを持っているということはそれに費やすことができた労力の量を端的に証明していることになる。誰にとってもその労働力の存在があったことが、明らかである。
この採掘コストの明示性が、ゴールドの価値をを生み出している。
「誰かがそれにコストを支払ったから価値がある」
もちろんゴールドにはそれに実用的な価値はないのだから、あくまで価値といっても最終的には幻想である。ではなぜその幻想が生まれるのかという根拠の部分を考えると、ゴールドを入手するためには必ずコストがかかるという部分に立脚しているのであろう。
古代の人々はゴールドを好んだが、これは美しいからではなく、王がもっている富の量を端的に示すことができたからであろう。100kgのゴールドがその王の前にあれば、だれもがその王が行使することができた労働力や力というものを理解できるからだ。だからゴールドに価値がある。
暗号通貨に関しては、ゴールドが持つ性質と極めて似ている性質をもつコインがある。PoWのマイニングを要するコインだ。
そうしたコインはマイニングによって算出され、必ずコストがかかる。具体的にはマイニング機材と電気代がかかる。そのコストは省略することが出来ず、どのような手段をつかっても必ずコストがかかる。マイニングをせずにコインを入手しようとすると、市場から購入することになるが、その場合マイニングにかかったコストと同様か高い値段で買うことになるのが通常だ。もし、市場価格がマイニングコストより安ければ、採掘事業者はコインを市場で購入するため、価格の下支えになる。
このような理論では、マイニングに要したコスト、つまり、1コインあたりの限界マイニングコストと市場価格は一致し、均衡する。すなわち、新規のコインは常に時価で発行される。
限界マイニング費用 = 発行価格 (≒時価)
端的にここまでの議論をまとめると、ゴールドのモデルを仮想化したものが、採掘価値説によるトークンである。
採掘価値説では、マイニングにコストがかかることが最も大事である。マイニングを要さないアルゴリズム(POSなどコストを掛ける必要がない仕組みの場合)、採掘価値説がなりたたないので、そのコインは価値を示すことができないことになる。同様に、プレマインによりコインのスタート時にすべてのコインが事前採掘されている場合は、無からコインを発行しているということになる。これは採掘価値説に反するので、時に詐欺であると指摘される。また採掘量は人為的に調整できず、上限があるほうがよい。
採掘価値説が成り立つには、
- PoWのアルゴリズムにより採掘にコストがかけられること、
- プレマインされず、コインは徐々に発行されること、発行量に上限があること
- 中央のコントロールがない・管理者がいないこと
の3つが必須の条件である。
採掘価値説では、まず良質の価値貯蔵手段(Sound money)が最初に有りきである。Sound moneyであるから、それを交換したり送金する需要もうまれ、意味をなすという考え方である。
一方で、採掘価値説のコインに対しては大きな疑念がある。一般のひとがいう意味での「通貨」には成り得ないだろうというものだ。採掘価値説のコインは、高価であり希少であることのみが存在理由であるため、基本的には日常の生活では使われない可能性が高い。また、供給量が限られることから、経済圏を成り立たせようとすると必ずデフレを招く。(お金の歴史的な流れを振りかると、かつて金本位制を採用していたためにデフレに悩まされ、経済の拡大に貨幣の供給量が追いつかず、物価も安定しなかった。そこで発明されたのが信用による紙幣であり、これは20世紀後半の世界の成長に寄与した。)
こうした経緯を考えると、採掘価値説のコインが、法定通貨を代替したり、ある経済圏の価値交換をまるごと担うという形になるのは難しいだろう。
採掘価値説のコインの主な用途は、政府や、特定の権力主体によらない、ポータブルで、プライバシーの高い価値の貯蔵手段としてのものである。
なお採掘価値説は、マルクスの労働価値説に似ている。そのため、労働価値説へのものと同様のロジックの反論が存在する。
「リンゴの栽培に1万円かかったとしても、そのリンゴは1万円の価値がないだろう。コインも一緒だ」
というもの。しかし、リンゴは食べて美味しいという実用的な用途がある。実用的な用途を持ちあわせてしまっていると、その実用を超える価格は正当化できない(リンゴの場合、ユーティリティトークンの価値算定方法と似たモデルになるだろう)。一方、ゴールドや暗号通貨には実用的な価値は全く無い。そのため純粋にかかったコストを価値に反映させることが可能になる。
まとめ
| 価値が生じるロジック | 一言で言うと | 現実世界の類似物 | 成立のテクニカル条件 | 理論 | その立場を取るコイン(推測) | |
| 交換価値説 | 信用。他人が受け取ること、経済圏で流通すること | 「誰かが受け取るから価値がある」 | 紙幣 | なし(コイン上限、アルゴリズム、初期配布、非中央集権、といった要件は必ずしも必要とされない。管理者がいて中央DB上でも実現できる) | M = GDP/V | ビットコインキャッシュ、リップル、IOTAなど |
| 採掘価値説 | 希少性。取得に高いコストがかかることが容易に証明できること | 「誰かがそれにコストを支払ったから価値がある」 | ゴールド | PoWによるマイニング・プレマインなし、 コインの上限、P2P の3条件が必須 |
限界マイニングコスト=発行価格 | ビットコイン、ライトコインなど |
対立する議論
この2つの議論は対立している。ただし、どちらの論も現実に存在する紙幣またはゴールドのモデルを模したものであり、どちらが間違っていて、どちらが正しいというものでもない。紙幣もゴールドもどちらも価値があり、成立しているからだ。
であるならば、論点は次のようになるであろう。
あなたが保有または関わっているコインは、
- 交換価値または採掘価値、どちらの色合いのコインなのだろうか?
を理解したうえで、あなたの目的(送金、貯蓄、投機)と照らしあわせて、
- 目的にあったものになっているか?
を考えてみるのがよいだろう。コインの保有だけでなく、コインを設計したり新しく作るときにも同様である。
・おしらせ
ビットコイン研究所の有料版サロンでは、平易な言葉で最近の技術や業界事情などについて解説するレポートを毎週配信しています。
暗号通貨について、もっと知りたい、勉強をしたいというかたに情報を提供しています。サロン内では疑問点も質問できます。
一度登録いただけると100本以上の過去レポートが読み放題で、大変お得です。レポート一覧がこちらのページありますので、よろしければいちど目をとおしてみてください。