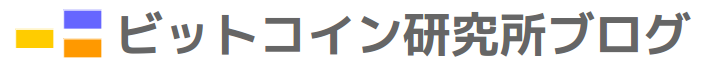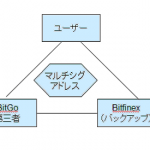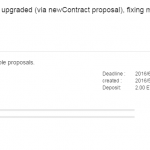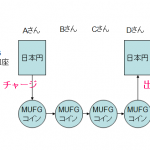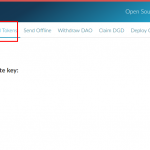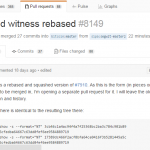レポート「アルトコイン図鑑」では30種類以上のコインを解説
レポート「ビットコインの情報源決定版(26ページ)」を配信しました。レポート内容へ
いま一番困っている誤解がこれである。
先日は、とんでもない表現をみた。
FinTechの本命技術と言われている 「ブロックチェーン」に基づく暗号通貨「ビットコイン」
というもの。もうどうにもこうにもならない誤解な気がして、どこから説明していいのかわからないくらいだが、本当にこういいう認識になってしまっているのかもしれない。
たしかに集合の包括関係を書くと、そういうことだとも言えなくもない

先の文章もこういうことをいいたのだろうが、やっぱり間違っている。
発明の経緯
まず、オリジナルのブロックチェーンは、フィンテックのために作られた技術ではなく、ビットコインの誕生と同時に発明されたものである。
ブロックチェーンは、ビットコインの誕生とともに同時に発明された。ビットコインを実現するために発明された技術と概念がブロックチェーンだ。なので、ビットコインと切っても切り離せない。
その後、この技術に目をつけた金融機関が、ブロックチェーンの技術を一部借用して、社内向けに使おうと考えたのが、いわゆる、プライベートレジャー(ブロックチェーン)である。
つまり、ビットコインから、公共の通貨の部分をそぎ落としてしまったのが、金融機関のブロックチェーンである。
これが正しい経緯である
しかしながらどうやら逆に捉えてる人も少なからずいるようだ。
つまり、ブロックチェーンという発明が先にあって、それを通貨に応用したのがビットコイン、他のものに応用したのがイーサリアム、金融機関に応用したのがMijinみたいな感じの順番であると思っている人が、いるということだ。
フィンテックとの関係
ビットコインとブロックチェーン、フィンテックの関係を言うと、前者と後者はというのは、もともと何ら関係がない。別々の人々が、まったく別々の概念として発展させてきたもので、接点はなかった。
イメージで言うと、ビットコインは、暗号オタクが作った通貨、フィンテックは銀行が考えたIT、といっ感じだろうか。
どちらからどちらが派生したということでもない。親と子の関係ではなく、まったく独立したふたつの概念なのだ。最近は、どうも、フィンテックという親のなかから、ビットコインまたはブロックチェーンという子供が生まれてきているというように理解されている。

意味合いの遷移を模式したのがこの図だ。
かつては、ビットコインのなかにブロックチェーンが位置づけられていた。
しかし、Afterでは、ブロックチェーンだけが抜き取られて、フィンテックに移植されている。
そして、ビットコインとフィンテックは交わってない。
日本では、ビットコインは敬遠されていて、フィンテックのほうが無難なキーワードになっている。
なので、フィンテックということにしたほうが話の通りが良いという大人の事情なのかマーケティングなのか、ビットコインとは言わずに、ブロックチェーンと言い換えたり、フィンテックって言い換えしまっている事が多い。
これはとんでもないミスリードだと思う。わけのわからん配慮から事実を捻じ曲げると、またガラパゴスになってしまうだろう。
詳細日本語マニュアル付きTrezorの購入は
初心者向け「使って勉強!ビットコイン」